
早川 誠司|生成AI活用コンサルタント/業務効率化アドバイザー


早川 誠司|生成AI活用コンサルタント/業務効率化アドバイザー
ChatGPTはWebサイトやアプリで対話的に利用するのが一般的ですが、「API(エーピーアイ)」を使うことで、開発者は自身のプログラムやサービスにChatGPTの機能を組み込むことができます。
APIとは?
簡単に言うと、ソフトウェア同士が情報をやり取りするための「接続口」のようなものです。ChatGPT APIを使えば、例えば以下のようなことが可能になります。
この記事では、ChatGPT APIを利用したいと考えている開発者や技術担当者の方に向けて、APIの基本、料金体系、そして特に誤解の多い「無料枠」について、さらにAPIキーの取得方法や簡単な使い方を解説します。
[chatgpt 無料 api], [chatgpt api 無料 枠] といった検索が多く見られますが、ここで非常に重要な点をお伝えします。
結論から言うと、2025年4月現在、OpenAI APIには継続的に利用できる「無料枠」は基本的に存在しません。
過去には、新規アカウント登録時に少額の無料クレジット(試用期間のようなもの)が付与されていた時期もありましたが、現在はこのプログラムは多くの場合停止されています。
OpenAIのドキュメントで「Free Tier」という言葉が出てくることがありますが、これは主にAPIの利用頻度に関する制限(レートリミット)の区分を指しており、「料金が無料」という意味ではありません。
APIを利用するためには、原則としてOpenAI Platformに支払い情報を登録し、従量課金で利用料金を支払う必要があります。 最低$5からのクレジット購入、または後払い設定が必要です。
この点を誤解していると、予期せぬ料金が発生する可能性があるため、十分に注意してください。
ChatGPT APIの利用料金は、主に「トークン」という単位に基づいた従量課金制です。
gpt-4o, gpt-4o-mini など)によって、1トークンあたりの単価が異なります。一般的に、高性能なモデルほど単価が高くなります。
| モデル例 | 入力 (100万トークンあたり) | 出力 (100万トークンあたり) | 特徴 |
gpt-4o | $5.00 | $15.00 | 最新・最高性能 (テキスト) |
gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | 高速・低コスト |
gpt-3.5-turbo | $0.50 | $1.50 | バランス型 (旧モデル) |
| (DALL-E 3など画像API) | (画像サイズ等による) | (画像サイズ等による) | 画像生成 |
(注意) 上記は料金例であり、常に変動する可能性があります。最新の正確な料金は、必ずOpenAI Pricingページで確認してください。
意図しない高額請求を防ぐために、OpenAI Platformの管理画面で利用上限額を設定したり、定期的に利用状況(Usage)を確認したりすることが非常に重要です。
APIを利用するための準備は以下の通りです。
.envなど)に保存し、プログラムから読み込む方法が推奨されます。APIキーが取得できたら、簡単なコードでAPIを呼び出してみましょう。以下はPythonのopenaiライブラリを使った例です。
Python
# pip install openai が必要
import os
from openai import OpenAI
# 環境変数からAPIキーを読み込むことを推奨
# client = OpenAI(api_key=os.environ.get("OPENAI_API_KEY"))
# 下記は直接キーを指定する例(非推奨)
client = OpenAI(api_key="あなたのAPIキーをここに貼り付け") # ← 安全な方法で管理してください!
try:
completion = client.chat.completions.create(
model="gpt-4o-mini", # 低コストなモデルでテスト
messages=[
{"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
{"role": "user", "content": "日本の首都はどこですか?"}
]
)
print(completion.choices[0].message.content)
except Exception as e:
print(f"エラーが発生しました: {e}")
pip install openai でライブラリをインストールしておきます。api_key には、先ほど取得したAPIキーを指定します(環境変数からの読み込みがベストプラクティスです)。model で利用するモデルを指定します。テスト段階では低コストな gpt-4o-mini などを使うのがおすすめです。messages でChatGPTに送る指示や質問を記述します。APIには、短時間に大量のリクエストを送ることを防ぐための「レート制限」があります。プランや利用状況に応じて、1分あたりに呼び出せる回数(RPM)やトークン数(TPM)に上限が設けられています。制限を超えるとエラーが発生するため、大量のリクエストを送る場合は、適切な待機処理(リトライ処理)などを実装する必要があります。
ChatGPT APIは、開発者にとって非常に強力なツールですが、その利用には正確な知識と注意が必要です。
これらの点を踏まえた上で、まずは少額のクレジットで低コストなモデルから試してみて、API連携の可能性を探ってみてはいかがでしょうか。
より詳細な情報や最新情報については、必ずOpenAI Platformの公式ドキュメントを参照してください。

3秒で登録完了!AI活用スタートガイド(PDF)
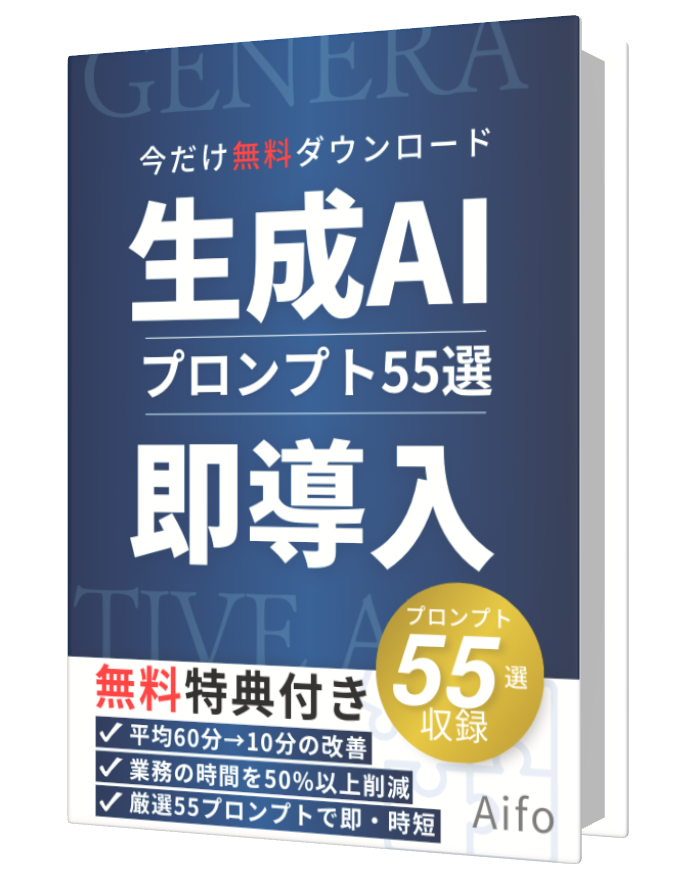
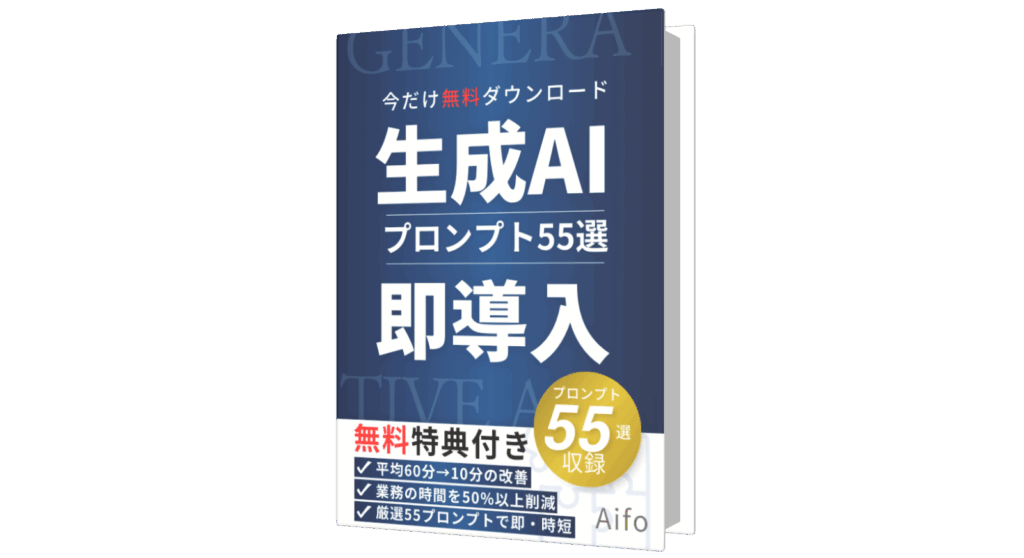
このガイド(PDF版)で、あなたのビジネスはこう変わります↓
✅ 面倒な作業が劇的に楽に! (資料作成、メール返信 etc.)
✅ 平均60分→10分! 驚きの時間短縮を実現。
✅ コピペOKの55選で、今日からすぐに効果を実感!
全55プロンプト収録の「AI業務効率化ガイド」PDF版を、ご入力いただいたメールアドレスへすぐにお送りします。
メールアドレスを入力するだけでOK!迷惑メール等は一切送りませんのでご安心ください。(いつでも解除可能です)
コピペするだけで業務が劇的に楽になる「AI業務効率化ガイド(全55プロンプト収録)」のPDF版をお送りします。
メールアドレスを入力するだけでOK!迷惑メール等は一切送りませんのでご安心ください。